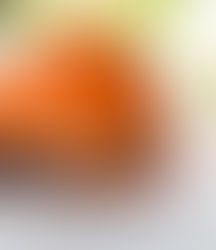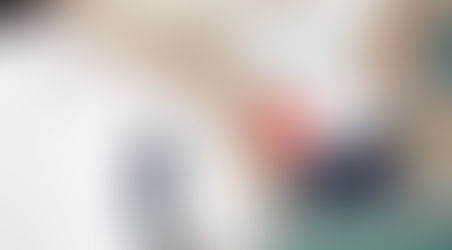キャリコンサルタント試験の面接試験の口頭試問対策
キャリコンサルタント試験の面接試験は、15分のロールプレイと5分間の口頭試問で構成されています。5分間の口頭試問も準備しないと不安ですよね。今回は、口頭試問で何を聞かれるのか、どう解答するのが良いのかというのを一緒に考えていきましょう。日本キャリア開発協会による面接試験につ...


YOLO(you only live once)な生き方とは
テレビを観ているとYOLO族という見慣れない言葉が聞こえてきました。You only live onceの頭文字を取った言葉らしいです。「人生一度きり」っていう意味ですね。 人生一度きりだから、楽しもう? テレビでは、エリート銀行マンが退職してストレスフリーなリゾート暮らし...


傾聴について(キャリアコンサルタント面接試験対策)
キャリアコンサルタント試験の面接試験の評価区分は、主訴・問題の把握、具体的展開、傾聴の3つです。今回は傾聴について考えていきます。面接試験で目指すことは、信頼関係の構築と自己探索の支援だと面接試験対策の記事で記載しましたが、この二つにつながる姿勢が傾聴と言えます。傾聴とは、...


具体的展開について(キャリアコンサルタント面接試験対策)
キャリアコンサルタント試験の面接試験の評価区分は、主訴・問題の把握、具体的展開、傾聴の3つです。この3つについてできているかどうかが判断されていきます。それぞれは何を意味するのか、何を意識すればよいのかを試験対策として事前に明確にしておきましょう。...


主訴・問題の把握について(キャリアコンサルタント面接試験対策)
キャリアコンサルタント試験の面接試験の評価区分は、主訴・問題の把握、具体的展開、傾聴の3つです。この3つについてできているかどうかが判断されていきます。それぞれは何を意味するのか、何を意識すればよいのかを試験対策として事前に明確にしておきましょう。...


キャリアコンサルタント試験 面接試験対策
キャリアコンサルタント試験の面接試験って、何の準備をしたら良いのでしょうか。ただひたすらロールプレイングを行うのも良いですが、大事なポイントを明確にしたうえでロールプレイングを行えばもっと効果的に練習を行えます。 日本キャリア開発協会の大事にしているポイントを確認しながら、...